「システム開発を発注したのに、納品されたものがイメージと違う…」そんな経験はありませんか?
システム・アプリ開発の検収書は、言った言わないのトラブルを防ぎ、スムーズなプロジェクト完了に欠かせない書類です。
初めてシステム開発を発注する方や、過去にトラブルを経験した方に向けて、検収書の基礎知識から具体的な作成方法、注意点までをわかりやすく解説します。
この記事を読めば、もう検収書で失敗することはありません。
この記事を読んでほしい人
- システム開発を初めて発注する人
- 過去に検収でトラブルを経験したことがある人
- システム開発における検収の重要性を理解したい人
この記事でわかること
- 検収書の基礎知識と作成方法
- 検収書を作成しなかった場合のリスクとトラブル事例
- 検収項目・検収基準の設定方法と具体例
システム・アプリ開発の検収書の役割

検収書は、開発プロジェクトにおいて、以下の4つの重要な役割を担っています。
- 品質保証:システムやアプリが仕様書通りに動作するか、不具合がないかなどを確認し、品質を保証する
- 合意形成:発注者と開発者の間で、システムやアプリの完成度について合意を得るための証拠となる
- トラブル防止:後から「こんなはずではなかった」といった認識のズレやトラブルを未然に防ぐ
- 円滑な引き渡し:システムやアプリの所有権や責任範囲を明確にし、スムーズな引き渡しを実現する
そのため、検収書は、発注者と開発者の双方が安心してプロジェクトを進めるための重要なツールといえるのです。
システム・アプリ開発の検収書がないとどうなるのか?具体的なリスクとトラブル事例

検収書を作成せずにシステムやアプリの開発を進めると、下記のようなリスクやトラブルが発生する可能性があります。
- システムに不具合があっても、開発会社が対応してくれない:検収書がない場合、システムに不具合があったとしても、開発会社が責任を認めず、修正に応じない
- 追加費用を請求される:検収書に記載されていない機能や修正を要求した場合、追加費用を請求される
- 納期が遅れる:検収基準が明確でない場合、開発が完了したと判断する基準が曖昧になり、納期が遅れる
- システムの所有権が不明確になる:検収書がない場合、システムの所有権が誰にあるのかが不明確になり、トラブルに発展する
- セキュリティ上の問題が発生する:セキュリティ対策が不十分なままシステムがリリースされ、情報漏洩などのセキュリティ上の問題が発生する
これらのトラブルは、プロジェクトの遅延やコスト増、企業の信頼失墜など、深刻な事態も引き起こす可能性があるため、検収書を作成することでリスクを回避し、安心してプロジェクトを進めましょう。
システム・アプリ開発の検収書の記載項目

ここでは、システム・アプリ開発の検収書の記載項目を解説します。
- 検収書の記載項目
- 検収項目の具体例
検収書を作成する際の参考にしてください。
検収書の記載項目
システム・アプリ開発の検収書には、以下の項目を記載することが一般的です。
- プロジェクト名
- 開発会社名
- 発注者名
- 検収日
- 検収場所
- 検収対象システム・アプリ
- 検収基準:システムやアプリが満たすべき機能や性能に関する基準
- 検収項目:検収基準にもとづいて具体的に確認する項目
- 検収結果:各検収項目の合否
- 不具合の有無:検収で発見された不具合の内容
- 今後の対応:不具合の修正方法やスケジュール
- 署名・捺印:発注者と開発者の署名と捺印
検収項目の具体例
検収項目の具体例をいくつか紹介します。
- 機能テスト:各機能が仕様書通りに動作するかを確認する
- 性能テスト:処理速度やレスポンス時間などが要件を満たしているかを確認する
- セキュリティテスト:セキュリティ上の脆弱性がないかを確認する
- ユーザビリティテスト:システムやアプリが使いやすいかを確認する
- 互換性テスト:異なるブラウザやOSで問題なく動作するかを確認する
検収基準にもとづいて具体的に確認する項目である検収項目を網羅的に設定すれば、システムやアプリの品質を確実に担保可能です。
ただし、これらのテストは、専門的な知識やツールが必要になる場合もあるため、必要に応じて専門家のサポートを受けることをおすすめします。
システム・アプリ開発の検収基準の具体的な設定方法

検収基準は、次の3つの観点から設定するようにし、開発前に発注者と開発者の間で十分に協議し、合意しておくことが重要です。
- 機能要件
- 性能要件
- 運用要件
検収基準は、システムやアプリが満たすべき機能や性能に関する基準となります。
検収基準が曖昧だと、検収時にトラブルが発生する可能性があるため、具体的に設定しましょう。
機能要件
機能要件では、システムやアプリが備えるべき機能を下記のように具体的に記載します。
- ユーザー登録・ログイン機能:ユーザーがアカウントを作成し、ログインできること
- 商品検索機能:キーワードやカテゴリで商品を検索できること
- カート機能:商品をカートに追加・削除できること
- 決済機能:クレジットカードや銀行振込などで決済できること
- 注文履歴表示機能:過去の注文履歴を確認できること
性能要件
性能要件では、システムやアプリが満たすべき処理速度やレスポンス時間などの性能を以下のように数値で記載します。
- レスポンス時間:各ページの表示速度が〇秒以内であること
- 同時アクセス数:〇〇人が同時にアクセスしても問題なく動作すること
- エラー発生率:エラー発生率が〇%以下であること
運用要件
運用要件では、システムやアプリを安定稼働させるために必要な環境や条件を次のように記載します。
- 稼働時間:24時間365日稼働すること
- セキュリティ対策:SSL通信の導入、ファイアウォールの設置など
- バックアップ体制:定期的なデータバックアップの実施
システム・アプリ開発の検収書発行の流れ

システム・アプリ開発の検収書の発行に際しては、下記の流れに沿って行うことが一般的です。
- 成果物を検収する
- 内容に問題がないことが確認できたら検収書の作成及び押印
- 検収書をベンダーへ送付
特にシステム・アプリなどの成果物を検収する際には、機能や画面のデザイン、操作性などが発注通りであるかを非常に細かくチェックしなければなりません。
1. 成果物を検収する
まずは、成果物を検収します。
一見発注通りに見えても、以下のような可能性もあるので、発注の担当者はもちろんのこと、実際に今後使用予定の従業員に試験的に使用してもらい、問題がないかチェックしてもらいましょう。
- 予期しない箇所でバグが発生する
- 使いにくい
また、自社の顧客や一般ユーザー向けに配信するようなアプリであるなら、複数の人間で問題がないか細部までチェックする必要があります。
なお、検収完了後に、不当なクレームをつけたり、契約解除を迫ったりすることはマナー違反となるので、注意してください。
2. 内容に問題がないことが確認できたら検収書の作成及び押印
成果物に問題がないことが確認でき次第、検収書を作成し、押印します。
3. 検収書をベンダーに送付
作成した検収書は、ベンダーに送付します。
郵送またはPDF化してメールで送付するかなど、検収書の送付方法については、事前に担当者間ですり合わせておき、行き違いが起きないようにしましょう。
システム・アプリ開発の検収書を作成可能なソフトウェア及びテンプレート

この章では、システム・アプリ開発の検収書を作成できるソフトウェア及びテンプレートをご紹介します。
- BtoBプラットフォーム 請求書
- freee for Salesforce
- HubSpot 検収書テンプレート
- マネーフォワード クラウド請求書
- Misoca
- MakeLeaps
検収書を作成する際、上記フォーマットやテンプレートがあると便利です。
BtoBプラットフォーム 請求書
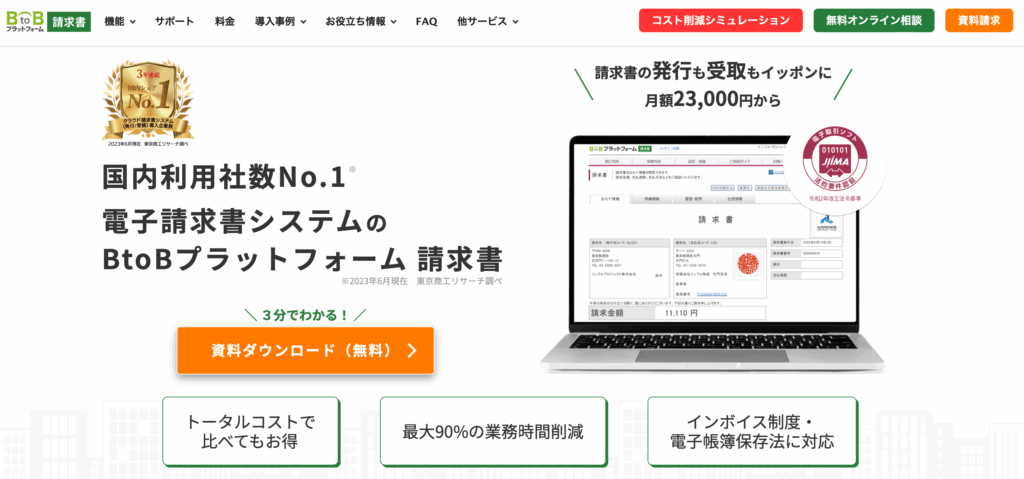
BtoBプラットフォーム 請求書は、あらゆる契約書を電子データとして、クラウド上で授受可能なソフトウェアです。
納品書の内容をそのまま検収書にトレースし、作成できます。
初期費用100,000円〜、月額利用料23,000円〜で、取引先は無料で利用可能です*。
*出典:BtoBプラットフォーム 請求書公式サイト「料金」2024年6月26日時点
freee for Salesforce
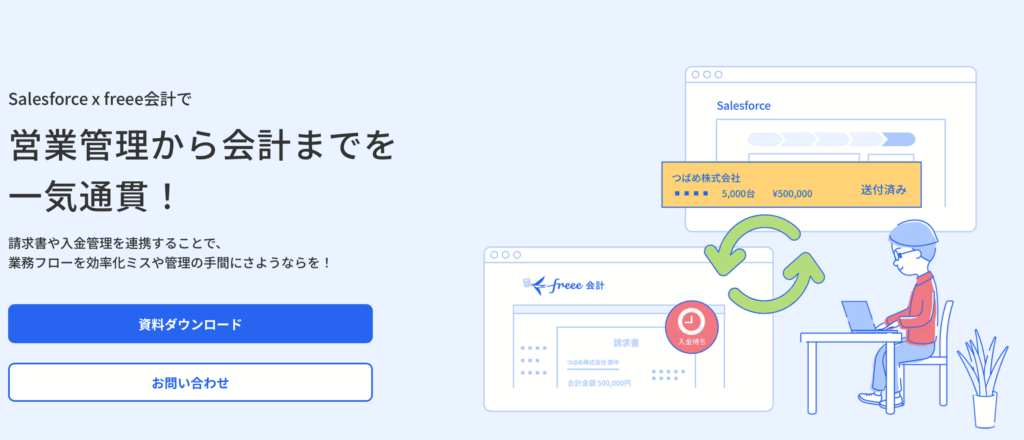
freee会計単体では、検収書を作成することはできませんが、Salesforceと連携することにより、検収書を作成可能です。
初期費用はかからず、無料で試せます*。
*出典:freee会計公式サイト「料金・プラン」2024年6月26日時点
HubSpot 検収書テンプレート
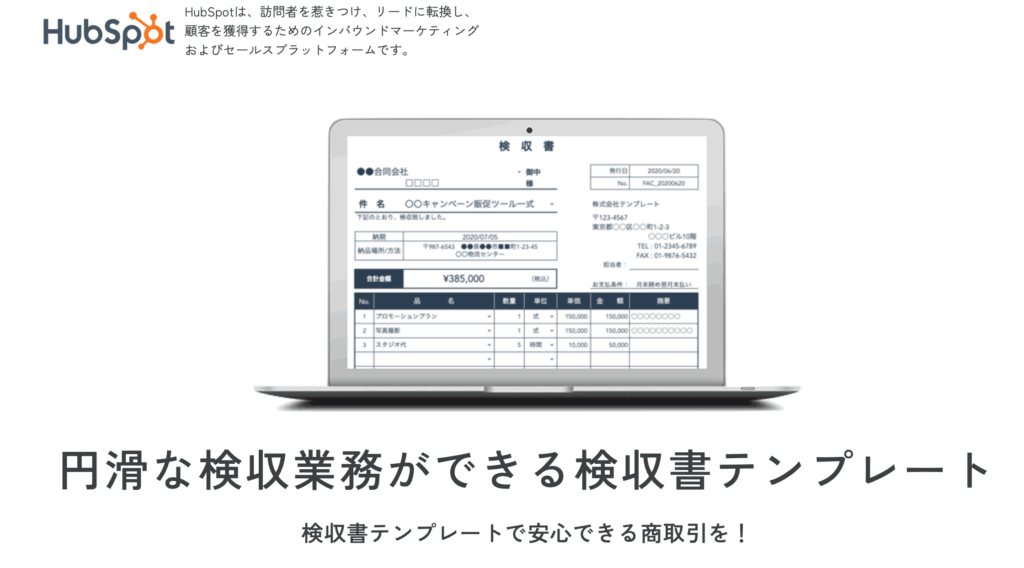
HubSpot無料テンプレートは、無料*ですぐにダウンロードできるテンプレートなので便利です。
検収項目の事前設定など直感的にわかりやすく入力できるので活用してみてください。
*出典:HubSpot 公式サイト「円滑な検収業務ができる検収書テンプレート」2024年6月26日時点
マネーフォワード クラウド請求書
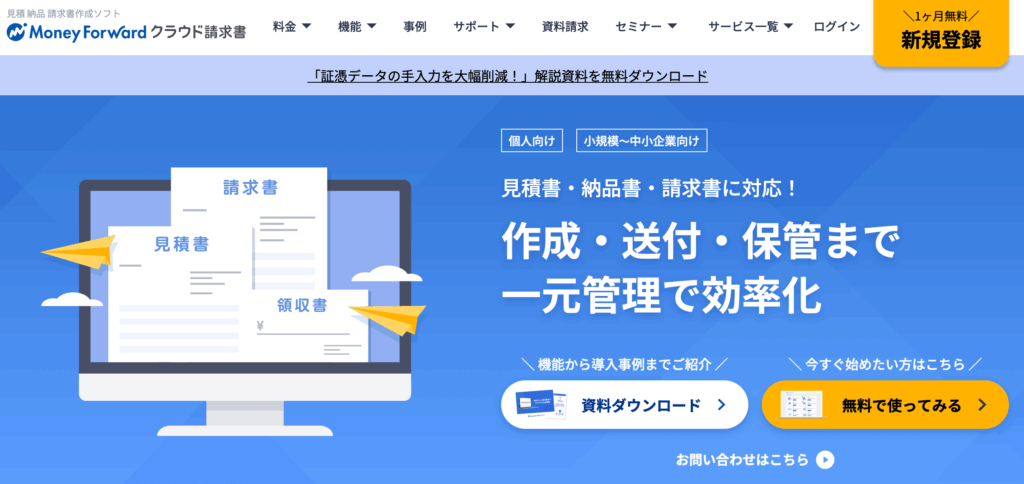
マネーフォワード クラウド請求書を用いることで、見積書あるいは納品書の情報をもとに、検収書を作成できます。
法人向けでもっとも安価なスモールビジネスプランは、年契約で月額料金2,980円*となっているので、予算を抑えて利用可能です。
*出典:マネーフォワード クラウド請求書公式サイト「マネーフォワード クラウド請求書の料金」2024年6月26日時点
Misoca

Misocaは、見積書、納品書、請求書を発行するためのサービスで有名ですが、検収書も発行可能です。
個人で月間の検収書発行枚数が少ない場合、ずっと無料*で利用できます。
また、小規模の法人なら、初年度1年間無料、2年目以降は年額9,680円(税込)で、同時利用人数2、15通までの請求書などの書類が作成可能です*。
*出典:Misoca公式サイト「料金プラン」2024年6月26日時点
MakeLeaps

MakeLeapsは、帳簿書類管理に特化したソフトウェアであり、検収書の発行も可能です。
ユーザー数上限3名の個人プランであれば、月額600円で、取引先上限10社の範囲で利用できます*。
*出典:MakeLeaps公式サイト「料金プラン」2024年6月26日時点
システム・アプリ開発の検収の流れ

システム・アプリ開発における具体的な検収の流れは、大きく分けて次の4工程となります。
- 受入れテスト
- プログラムの修正
- プログラムの再納品
- 受入れ再テスト
検収書を発行する前に、工程に沿って検収を行いましょう。
1. 受入れテスト
検収の第1段階である受入れテストは、クライアントが網羅的に行うもっとも重要なチェックです。
細かく分けると下記の5つに分類できます。
機能テスト
機能テストでは、システムやアプリが実際に稼働した際のあらゆる状況を想定し、さまざまなテストデータを用いて、システム・アプリが問題なく動作するか、要件定義書及び仕様書通りの機能要件を満たしているかなどを検証します。
具体的には、正しいデータ入力と操作によって正しい値が返されるかを確認する正常系テストや、意図的に誤ったデータ入力と操作を行い、システム・アプリの反応を確認する異常系テストを行うのが特徴です。
ユーザビリティテスト
ユーザビリティテストでは、システム・アプリを実際に利用するユーザーを想定し、使いやすいかどうか、業務フローや顧客のサービス利用を想定した現実的なシナリオにもとづいて、使用感や操作性を確認します。
具体的には、業務フローを妨げるようなインターフェースになっていないか、クリックボタンなどが誤操作を誘発する配置や仕様になっていないかなどを細かくチェックするのが特徴です。
疎通テスト
疎通テストでは、既存の自社システムや外部システムと、成果物が問題なく連携できるかを確認します。
セキュリティテスト
セキュリティテストでは、万が一のサイバー攻撃に耐え得るシステム・アプリであるかを確認します。
負荷テスト
負荷テストでは、成果物に意図的に大きな負荷をかけ、処理能力を測る性能テストや、想定される長時間連続稼働に耐えられるかどうかのロングランテスト、トラフィックが急増した場合の耐久性を測るキャパシティテストを実施します。
2. プログラムの修正
受入れテストで不具合が発見された場合、ベンダーにプログラムの修正を依頼します。
修正内容と再納品までのスケジュールについて、事前に合意しておくことが重要です。
3. プログラムの再納品
ベンダーがプログラムを修正した後、再度納品してもらいます。
修正内容が適切に反映されているかを確認するため、再納品されたプログラムのバージョンや修正内容を記録しておくことが重要です。
4. 受入れ再テスト
プログラムの修正と再納品が行われた場合、1回目の受入れテストで不具合が発見された箇所を中心に再度テストを行います。
修正が正しく行われているか、新たな不具合が発生していないかなどを確認しましょう。
システム・アプリ開発の検収における課題と解決策

ここでは、システム・アプリ開発の検収における代表的な課題とその解決策を紹介します。
- 課題1. 検収基準の曖昧さ
- 課題2. 検収項目の漏れ
- 課題3. コミュニケーション不足
システム・アプリ開発の検収はプロジェクトの成否を左右する重要なプロセスですが、さまざまな課題も存在するので、目をとおしておきましょう。
課題1. 検収基準の曖昧さ
検収基準が曖昧な場合、「これは検収対象外だ」「この機能は想定と違う」といったトラブルが発生しやすくなります。
<解決策>
- 検収基準を具体的に定義する
- モックアップやプロトタイプを活用する
- 定期的な進捗確認を行う
課題2. 検収項目の漏れ
検収項目が不足していると、重要な機能や性能がテストされず、不具合が残ったままシステムやアプリがリリースされてしまう可能性があります。
<解決策>
- 検収項目を網羅的に洗い出す
- 過去の事例を参考にする
- 専門家の意見を聞く
課題3. コミュニケーション不足
発注者と開発者の間でコミュニケーションが不足すると、認識のズレが生じやすく、検収時にトラブルが発生する可能性が高まります。
<解決策>
- チャットツールやビデオ会議ツールなどを活用し、密なコミュニケーションを心掛ける
- 定期的に進捗報告会を実施し、進捗状況や課題を共有する
- 仕様書や設計書、テスト結果などのドキュメントを共有し、認識を一致させる
システム・アプリ開発の検収にまつわる法的な側面

システム・アプリ開発の検収は、単なる事務手続きではなく、法的にも重要な意味をもつので解説していきます。
- 契約不履行
- 瑕疵担保責任
- 検収書と契約書の関係
- 専門家の活用
検収書は、システムやアプリが契約内容を満たしていることを証明する書類なので、後々のトラブルを回避するためにも、法的な側面を理解しておきましょう。
契約不履行
取引相手が契約内容通りのシステムやアプリを提供しない場合、債務不履行に該当する可能性があります。
検収書は、システムやアプリが契約内容に適合しているかを確認する重要な証拠となるので、必ず発行しましょう。
瑕疵担保責任
取引相手が納品したシステムやアプリに瑕疵(欠陥)があった場合、開発会社は瑕疵担保責任を負うことになります。
検収書に記載された内容にもとづき、瑕疵の有無や範囲を判断することが可能です。
検収書と契約書の関係
検収書は、契約書と合わせて、システム・アプリ開発における重要な法的文書で、検収書は、契約書の内容を具体的に実現するための手段として機能することを覚えておきましょう。
契約書に検収に関する条項が記載されている場合は、その内容に従って検収を行う必要があります。
専門家の活用
検収にまつわる法的な問題は複雑な場合があるため、必要に応じて、弁護士などの専門家に相談することも検討しましょう。
専門家のアドバイスを受けることで、法的なリスクを最小限に抑えられます。
システム・アプリ開発の検収書に関するよくある質問

この章では、システム・アプリ開発の検収書に関するよくある質問について、Mattockシニアコンサルタントが回答します。
- Q1. システム・アプリ開発の検収書は必要ですか?
- Q2. システム開発における検収とは?
- Q3. 検収書はどちらが作成するのでしょうか?
- Q4. システム・アプリ開発の検収書に記載する項目は?
- Q5. 検収は何日以内に行わなければならないか?
- Q6. システム・アプリ開発の検収書は何のため?
- Q7. 検収書に社印は不要ですか?
- Q8. システム・アプリ開発の検収書に署名するのは誰ですか?
システム・アプリ開発の納品でトラブルを避けるために、目をとおしておきましょう。
Q1. システム・アプリ開発の検収書は必要ですか?
システム・アプリ開発の検収書は必要です。検収書は、システムやアプリが契約通りに開発されたことを確認し、後々のトラブルを防ぐための重要な書類となります。
口頭での合意だけでは、認識の齟齬が生じる可能性があり、法的にも有効性が低くなるので、必ず作成しましょう。
Q2. システム開発における検収とは?
システム開発における検収とは、発注者が開発会社から納品されたシステムやアプリが、契約内容や仕様書通りに動作するかを確認する作業です。
検収は、機能テスト、性能テスト、セキュリティテストなど、多岐にわたる検証作業を含みます。
Q3. 検収書はどちらが作成するのでしょうか?
基本的に、検収書は取引相手が作成し、発注者が内容を確認・承認する流れが一般的です。
ただし、契約内容によっては、発注者が検収書を作成する場合もあります。
Q4. システム・アプリ開発の検収書に記載する項目は?
システム・アプリ開発の検収書には、以下の項目を記載することが一般的です。
- システム・アプリの名称
- 契約内容
- 検収基準(仕様書など)
- 検収実施日
- 検収結果(合格・不合格)
- 不具合や修正事項
- 双方の署名・捺印
Q5. 検収は何日以内に行わなければならないか?
法律で定められた期限はありませんが、契約書に検収期間が記載されている場合は、その期間内に実施する必要があります。
Q6. システム・アプリ開発の検収書は何のため?
システム・アプリ開発の検収書は、下記の目的で作成されます。
- 開発会社が契約を履行したことを証明する
- システム・アプリの品質を保証する
- 後々のトラブルを防止する
- 支払いの根拠とする
Q7. 検収書に社印は不要ですか?
検収書に必ずしも必要ではありませんが、押印することで、より正式な書類としての効力をもつと考えられます。
特に、契約書に押印が規定されている場合は、検収書にも押印することが望ましいです。
Q8. システム・アプリ開発の検収書に署名するのは誰ですか?
システム・アプリ開発の検収書には、発注側と開発側の双方の責任者が署名するのが一般的です。
発注側では、システム・アプリの導入責任者や担当部署の責任者、開発側では、プロジェクトマネージャーや開発責任者が署名することが多い傾向にあります。
まとめ
システム・アプリ開発における検収書は、プロジェクトの成功に欠かせない重要な書類です。
検収書を適切に作成し、活用することで、高品質なシステムやアプリを開発し、円滑なプロジェクト運営を実現できます。
Mattockのシステム・アプリ開発、オフショア開発支援サービス
Mattockは、システム開発・アプリ開発、ベトナムオフショア開発の豊富な実績とノウハウを活かし、お客様のニーズに合わせた最適なソリューションをご提案いたします。
- システム・アプリ開発:要件定義から設計、開発、テスト、運用保守まで、ワンストップでサポート
- ベトナムオフショア開発:ベトナムの優秀なエンジニアを活用し、高品質かつ低コストな開発を実現
- ラボ型契約:開発チームを一定期間確保するラボ型契約で、柔軟かつ迅速な開発が可能
- 業務効率化コンサルティング:業務プロセスを分析し、システム導入による業務効率化を支援


