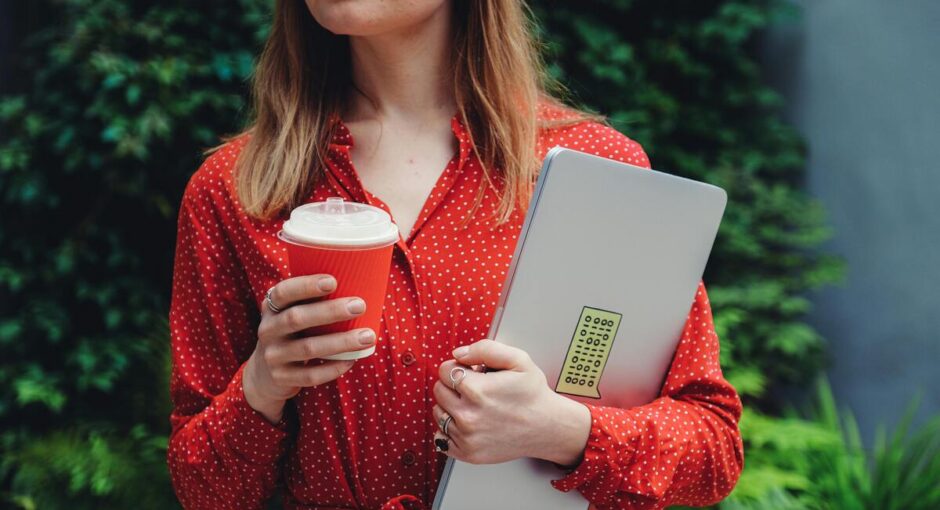労働時間管理の厳格化に伴い、多くの企業が勤怠管理システムの刷新を検討しています。
本記事では、システム開発プロジェクトの立ち上げから運用までを、実践的なアプローチと具体的な実装方法を交えて解説します。
特に注目すべきは、導入企業での管理工数70%削減を実現した効率的な開発手法です。最新のテクノロジーと法改正に対応した、信頼性の高い勤怠管理システムの構築方法をご紹介します。
この記事で分かること
- 勤怠管理システム開発における要件定義から実装までの具体的な手順と注意点
- 労働基準法や働き方改革関連法に準拠したシステム設計の重要ポイント
- 承認フローやデータ集計機能の効率的な実装方法とユースケース
- 業種別のカスタマイズ方法と、導入による具体的な改善効果
- トラブルシューティングとパフォーマンスチューニングの実践テクニック
この記事を読んでほしい人
- 勤怠管理の効率化とコスト削減を検討している人事部門責任者の方
- 社内システムの刷新を計画しているシステム企画担当者の方
- 勤怠管理システムの開発プロジェクトを主導するプロジェクトマネージャーの方
- 労務管理の法令順守と業務効率化の両立を目指す経営層の方
勤怠管理システム開発の基本要件
勤怠管理システムの開発では、法令順守と業務効率化を両立する必要があります。
本セクションでは、システム開発において押さえるべき基本要件を、具体的な実装方法と合わせて解説します。
特に重要となる労働時間管理、シフト管理、申請承認の各機能について、詳細な要件と実装のポイントをご紹介します。
労働時間管理機能
労働基準法に準拠した労働時間の正確な記録と管理は、勤怠管理システムの中核を担う機能です。2024年4月からの労働時間把握に関する法改正にも対応する必要があります。
出退勤時刻の記録システム
ICカードやスマートフォンを活用した打刻システムでは、なりすまし防止や位置情報との連携が重要です。
打刻データは暗号化してサーバーに送信し、改ざん防止措置を講じる必要があります。また、タイムスタンプ付きで記録を保持し、事後の確認や監査に備えます。
休憩時間の自動計算ロジック
労働基準法で定められた休憩時間の適切な管理を実現します。勤務時間に応じた休憩時間の自動計算、休憩取得状況の可視化、休憩未取得者へのアラート通知などの機能を実装します。
残業時間の集計機能
法定労働時間と所定労働時間の管理、36協定の特別条項への対応など、きめ細かな残業管理を実現します。月次の残業時間上限を監視し、上限超過の予兆を検知した際は、管理者へ自動通知する機能も実装します。
変形労働時間制への対応
1年単位、1ヶ月単位、フレックスタイム制など、多様な働き方に対応する必要があります。労働時間の集計期間や清算期間の設定、実労働時間の過不足管理など、柔軟な設定が可能なシステムを構築します。
シフト管理機能
効率的な人員配置と労働時間管理を実現するシフト管理機能は、特に小売業やサービス業において重要です。
シフトパターンの登録管理
部署や職種ごとの標準的なシフトパターンを登録し、効率的なシフト作成を支援します。季節変動や繁閑期に応じたシフトパターンの切り替えにも対応します。
勤務希望の収集と調整
従業員からの勤務希望をシステム上で収集し、自動でシフト案を作成します。希望シフトの重複や人員配置の偏りを自動検出し、調整案を提示する機能も実装します。
シフト表の自動生成
AIを活用した最適なシフト生成アルゴリズムにより、人件費の最適化と従業員の希望を両立するシフト表を作成します。過去の来客データや売上データと連携することで、より精度の高いシフト設計が可能になります。
申請承認機能
ペーパーレス化による業務効率化を実現する申請承認機能は、システムの利便性を大きく左右します。
休暇申請の電子化
年次有給休暇、特別休暇、育児・介護休暇など、各種休暇の申請と承認をシステム上で完結します。休暇取得率の可視化や取得促進のための通知機能も実装します。
残業申請のワークフロー
事前の残業申請と承認、実績の事後承認など、柔軟なワークフローを設定可能です。36協定の上限時間との照合や、予算管理との連携も重要な要件となります。
勤怠修正申請の管理
打刻漏れや修正が必要な場合の申請フローを電子化します。修正履歴の保持や承認権限の設定、監査証跡の記録など、厳格な管理を実現します。
以上の基本要件を満たすシステムを構築することで、法令順守と業務効率化の両立が可能となります。
次章では、これらの要件を実現するための具体的な開発アプローチについて解説します。
システム開発の実践的アプローチ
勤怠管理システムの開発を成功に導くためには、体系的なアプローチと実践的な開発手法が不可欠です。
本セクションでは、要件定義から実装まで、各フェーズにおける具体的な手順とベストプラクティスをご紹介します。特に重要となるデータモデルの設計や、開発プロセスの効率化についても詳しく解説します。
要件定義フェーズ
システム開発の成否を決める重要な段階である要件定義フェーズでは、現状の課題分析から始めることで、より効果的な要件定義が可能となります。
現状分析の実施手順
現在の勤怠管理における課題を、定量的なデータと定性的な情報の両面から分析します。具体的には、まず管理部門へのヒアリングを実施し、日々の業務における課題点を洗い出します。
次に、現場の従業員に対してアンケート調査を行い、使用感や改善要望を収集します。これらの情報を基に、システム化による改善が見込める領域を特定していきます。
業務フローの可視化プロセス
現状の業務フローを詳細に分析し、非効率な部分や改善ポイントを特定します。まず、打刻から給与計算までの一連の流れを時系列で整理します。
次に、各プロセスにおける所要時間や、関係者の動きを図式化します。
この過程で、承認フローの複雑さや、データ入力の重複といった課題が明確になってきます。
要件の優先順位付け方法
開発要件をビジネス価値と実装の複雑さの観点から評価し、優先順位を決定します。法令順守に関わる機能は最優先とし、続いて業務効率化に直結する機能、そして付加的な分析機能という順序で実装を計画します。
優先順位付けの際は、ステークホルダーの意見を広く集め、組織全体のコンセンサスを得ることが重要です。
システム設計フェーズ
システム設計フェースでは、将来的な拡張性とメンテナンス性を考慮した設計を行います。特に重要となるのが、データモデルの設計とシステムアーキテクチャの策定です。
データモデル設計の重要ポイント
効率的なデータ管理を実現するため、以下の点に注意してテーブル設計を行います。まず、従業員マスターでは、雇用形態や所属部署といった基本情報を管理します。次に、勤怠データテーブルでは、日々の勤務記録を時系列で保存します。
さらに、承認フローテーブルでは、申請種別ごとの承認ルートを柔軟に設定できる構造とします。これらのテーブル間の関連性を適切に設計することで、データの整合性と検索効率を確保します。
システムアーキテクチャの設計方針
システム全体のアーキテクチャは、フロントエンド、バックエンド、データベースの3層構造で設計します。フロントエンドは、スマートフォンやタブレットからのアクセスを考慮し、レスポンシブデザインを採用します。
バックエンドは、APIベースの設計とし、将来的な機能追加や外部システムとの連携に備えます。データベースは、大量のトランザクション処理に対応できる堅牢な設計とします。
開発・実装フェーズ
実装フェーズでは、品質とユーザビリティの両立を目指します。開発手法には、アジャイル開発を採用し、短いサイクルでのフィードバックと改善を繰り返します。
フロントエンド実装のアプローチ
ユーザーインターフェースの実装では、直感的な操作性を重視します。勤怠入力画面では、カレンダー形式での表示を基本とし、スワイプやタップでの簡単な操作を実現します。
また、入力値のリアルタイムバリデーションにより、エラーを未然に防ぐ仕組みを実装します。画面遷移は、ユーザーの作業フローに沿った自然な流れとなるよう設計します。
バックエンド実装の考え方
サーバーサイドの実装では、セキュリティと性能の両立を図ります。APIの設計では、RESTful原則に従い、直感的なエンドポイント構成とします。
データベースアクセスは、コネクションプールを適切に管理し、高負荷時でも安定したレスポンスを維持します。
また、バッチ処理による集計作業は、システム負荷の少ない深夜時間帯に実行するよう設計します。
テスト戦略と品質保証
開発過程での品質確保のため、複数層でのテストを実施します。ユニットテストでは、各機能の動作を個別に検証します。
結合テストでは、モジュール間の連携を確認します。
さらに、実際の業務シナリオに基づいた総合テストを行い、システム全体の整合性を検証します。
特に、月末の給与計算時期を想定した負荷テストは重点的に実施します。
以上のアプローチに基づき開発を進めることで、高品質な勤怠管理システムを実現できます。
次章では、これらの基本設計を元に、業種別のカスタマイズ方法について解説します。
業種別カスタマイズガイド
勤怠管理システムは、業種ごとに求められる要件や運用方法が大きく異なります。
本セクションでは、製造業、サービス業、小売業それぞれの特性に応じたカスタマイズ方法と、実際の導入事例から得られた知見をご紹介します。
製造業向け実装ガイド
製造業では、シフト制や交代制勤務への対応が特に重要となります。また、生産計画との連携や残業管理の厳格化が求められます。
シフトパターン管理の実装
製造ラインごとの稼働時間に合わせて、複数のシフトパターンを柔軟に設定できる仕組みを実装します。早番、遅番、夜勤などの基本シフトに加えて、繁忙期の特別シフトも管理できるよう設計します。
さらに、作業員の技能レベルや資格情報と連携させることで、各シフトで必要な人員配置を最適化します。
生産計画との連携機能
生産管理システムと連携し、生産計画に基づいた人員配置の最適化を実現します。ラインごとの必要人数を自動計算し、シフト作成時の参考値として活用できる機能を実装します。
また、急な生産計画の変更にも対応できるよう、シフトの柔軟な調整機能も備えます。
サービス業向け実装ガイド
サービス業では、変動する顧客需要に応じた柔軟なシフト管理が必要です。また、複数店舗での勤務管理や、パートタイム従業員の効率的なスケジュール管理も重要となります。
需要予測に基づくシフト最適化
過去の来客データや売上データを分析し、時間帯別の必要人員を予測する機能を実装します。天候や地域イベントなどの外部要因も考慮に入れ、より精度の高いシフト計画を立案できるようにします。
また、リアルタイムの顧客数や売上状況に応じて、シフトの微調整を行える機能も追加します。
マルチロケーション対応
複数店舗での勤務管理を効率化するため、店舗間での従業員シフトの調整機能を実装します。従業員の移動時間や交通費も考慮した最適な人員配置を支援します。
また、店舗ごとの売上目標や人件費予算との整合性も確認できるようにします。
小売業向け実装ガイド
小売業では、繁忙期と閑散期の差が大きく、アルバイトスタッフの効率的な配置が課題となります。また、売上データとの連携による人件費の最適化も重要です。
売上連動型シフト管理
時間帯別の売上データと人員配置の相関を分析し、最適な人員配置を提案する機能を実装します。特に、レジ待ち時間の目標値を設定し、それを満たすために必要な人員を自動算出する機能は、顧客満足度の向上に貢献します。
短時間勤務者の最適配置
学生アルバイトなど、短時間勤務者の効率的な配置を支援する機能を実装します。勤務可能時間帯や最低勤務時間、希望シフトなどの制約条件を考慮しながら、店舗の必要人員を満たすシフトを自動生成します。
また、シフト調整時の連絡や確認作業を効率化する機能も備えます。
業種共通の拡張機能
すべての業種で活用できる拡張機能として、勤怠データの分析機能があります。労働時間の傾向分析や、人件費の予実管理、生産性分析などを可能にします。
また、従業員のワークライフバランスを考慮したシフト作成支援機能も、業種を問わず重要性が高まっています。
このように、業種ごとの特性を理解し、適切なカスタマイズを行うことで、より効果的な勤怠管理システムを実現できます。
次章では、システム導入後によく発生するトラブルとその解決方法について解説します。
トラブルシューティング
勤怠管理システムの運用において、様々なトラブルが発生する可能性があります。
本セクションでは、実際の導入事例から得られた知見を基に、よくある問題とその解決策、さらにはシステムの性能改善方法について解説します。
よくある問題と解決策
システム導入後によく発生する問題に対して、効果的な解決アプローチをご紹介します。
データ同期の遅延対策
複数の拠点や端末間でのデータ同期の遅延は、正確な勤怠管理の妨げとなります。この問題に対しては、まずデータベースのインデックス最適化を行います。
特に、頻繁にアクセスされる勤怠記録テーブルのクエリパフォーマンスを重点的に改善します。また、同期処理の実行間隔を調整し、ネットワーク負荷の分散を図ることで、安定した運用を実現できます。
承認フローの停滞解消
承認者の不在や確認漏れによる承認フローの停滞は、給与計算等の後続処理に影響を及ぼします。この問題を解決するため、承認期限が近づいた申請に対する自動リマインド機能を実装します。
また、承認者が不在の場合の代理承認ルールを明確化し、システムに組み込むことで、スムーズな処理を実現します。
打刻忘れへの対応
従業員の打刻忘れは、正確な勤務時間管理を困難にします。この対策として、勤務開始時刻になっても打刻がない場合のアラート機能を実装します。
さらに、PCのログイン・ログアウト時刻との連携や、スマートフォンの位置情報を活用した自動打刻機能の導入も効果的です。
性能改善とチューニング
システムの安定運用のため、定期的な性能改善とチューニングが重要です。
データベースの最適化
大量の勤怠データを扱うシステムでは、データベースのパフォーマンスが重要です。定期的なインデックスの再構築や、パーティショニングの導入により、検索速度を改善します。
また、不要なデータの適切なアーカイブ処理を実装し、データベースの肥大化を防ぎます。
バッチ処理の効率化
日次・月次の集計処理など、大量データを扱うバッチ処理の最適化も重要です。処理をより小さな単位に分割し、並列実行することで、処理時間を短縮します。
また、システム負荷の少ない深夜帯にバッチ処理を実行するようスケジューリングを行います。
キャッシュ戦略の改善
よく参照されるマスターデータや、集計結果のキャッシュ戦略を見直します。適切なキャッシュ期間の設定と、キャッシュの自動更新の仕組みを実装することで、システムの応答性を向上させます。
また、分散キャッシュの導入により、大規模システムでの性能改善も実現できます。
監視体制の強化
システムの安定運用には、適切な監視体制の構築が不可欠です。CPU使用率、メモリ使用量、ディスクI/O、ネットワークトラフィックなどの主要メトリクスを常時監視し、問題の早期発見と対応を可能にします。
また、エラーログの分析により、潜在的な問題を特定し、予防的な対策を講じることができます。
以上のトラブルシューティングと性能改善施策により、安定した勤怠管理システムの運用が可能となります。
次章では、システムのセキュリティ対策について解説します。
セキュリティ対策
勤怠管理システムは個人情報や労務データを扱うため、高度なセキュリティ対策が不可欠です。
本セクションでは、データ保護の実装方法と、認証・認可の設計について、具体的な施策をご紹介します。
データ保護の実装
勤怠データや個人情報を確実に保護するため、多層的なセキュリティ対策を実装します。
データ暗号化の導入
システム内で扱う重要データの暗号化は、情報漏洩対策の基本となります。保存データの暗号化では、個人情報や給与関連情報などの機密データを対象とし、業界標準の暗号化アルゴリズムを採用します。
また、データベースへの保存時に自動的に暗号化が行われる仕組みを実装することで、運用担当者の負担を軽減します。
バックアップ体制の構築
データ消失や障害に備えたバックアップ体制を整備します。日次での増分バックアップと、週次での完全バックアップを組み合わせることで、効率的なバックアップを実現します。
また、バックアップデータの保管場所は、地理的に離れた場所に設置し、災害時のリスク分散を図ります。
アクセスログの管理
システムへのアクセスログを詳細に記録し、不正アクセスの検知や、情報漏洩の事後調査に備えます。特に、個人情報の閲覧や変更操作については、操作者の特定が可能な形でログを保持します。
これらのログは、定期的な監査の対象とし、不審な操作パターンの早期発見に活用します。
認証・認可の設計
システムの利用者を適切に認証し、必要な権限のみを付与する仕組みを構築します。
多要素認証の実装
システムへのログインには、パスワードに加えて、スマートフォンによる認証コードの入力を必須とします。特に、管理者権限でのログインや、給与情報へのアクセスには、より厳格な認証プロセスを設けます。
また、定期的なパスワード変更を強制する機能も実装します。
権限管理の細分化
システムの利用権限を、業務内容や役職に応じて細かく設定します。
一般従業員は自身の勤怠データの閲覧と申請のみ、管理者は部署内の従業員データの管理、システム管理者は全社的な設定変更権限というように、段階的な権限設定を行います。
また、特定の期間のみ有効な一時的な権限付与機能も実装します。
セッション管理の強化
ログインセッションの管理を厳格化し、セキュリティリスクを低減します。一定時間操作がない場合の自動ログアウト、同一アカウントでの複数端末からのログイン制限、セッションハイジャック対策などを実装します。
また、ログアウト時には確実にセッション情報を破棄する仕組みを設けます。
定期的なセキュリティ監査
システムのセキュリティレベルを維持するため、定期的な監査を実施します。外部の専門家による脆弱性診断や、内部での運用状況の確認を通じて、セキュリティ上の課題を早期に発見し、対策を講じます。
また、従業員向けのセキュリティ教育も定期的に実施し、システムの安全な利用を促進します。
インシデント対応計画
セキュリティインシデントが発生した際の対応手順を、あらかじめ明確化します。情報漏洩や不正アクセスが検知された場合の初動対応、関係者への連絡、被害の最小化、原因究明、再発防止策の策定といった一連の流れを、マニュアルとして整備します。
また、定期的な訓練を実施し、実効性の高い対応体制を維持します。
以上のセキュリティ対策により、安全かつ信頼性の高い勤怠管理システムの運用が可能となります。
次章では、実際の導入事例とその効果について解説します。
導入事例
勤怠管理システムの導入効果を具体的にご理解いただくため、本セクションでは異なる業種における実際の導入事例をご紹介します。
それぞれの企業が直面していた課題と、システム導入によってどのような改善を実現できたのかを詳しく解説します。
製造業A社の事例
大手製造業A社では、複数工場での勤怠管理の統合と、法令順守の徹底が課題となっていました。システム導入を通じて、大幅な業務効率化を実現しています。
導入前の課題
工場ごとに異なる勤務体系と承認プロセスが存在し、本社での一元管理が困難な状況でした。また、紙ベースでの申請承認により、月末の給与計算業務に多大な工数が発生していました。
残業時間の正確な把握も課題となっており、36協定の遵守状況の確認に時間を要していました。
システム導入のポイント
全社統一の勤怠管理プラットフォームを構築し、工場ごとの勤務体系や承認フローをシステム上で柔軟に設定できる仕組みを実装しました。
また、生産管理システムとの連携により、製造ラインの稼働状況と連動した勤務シフトの最適化を実現しています。
導入後の成果
システム導入により、勤怠管理業務の工数を70%削減することに成功しました。また、リアルタイムでの残業時間の可視化により、36協定の遵守管理が容易になり、法令順守体制が強化されています。
サービス業B社の事例
全国展開する飲食チェーンB社では、多店舗での勤怠管理の効率化と、人件費の最適化が課題でした。システム導入により、大幅なコスト削減を達成しています。
導入前の課題
店舗ごとに勤務シフトの作成方法が異なり、人員の最適配置ができていませんでした。また、アルバイトスタッフの勤務時間管理が不正確で、人件費の無駄が発生していました。
繁閑の差が大きい店舗では、適切な人員配置が困難な状況でした。
システム導入のポイント
売上予測データと連携したシフト最適化機能を実装し、店舗ごとの必要人員を自動算出する仕組みを導入しました。また、スマートフォンでの打刻を可能にし、位置情報との連携により、正確な勤務時間管理を実現しています。
導入後の成果
人件費を全社で15%削減し、同時に従業員の労働時間の適正化も実現しました。また、シフト作成にかかる時間を90%削減し、店長の業務効率が大幅に向上しています。
小売業C社の事例
大手小売チェーンC社では、パートタイム従業員の勤務管理と、繁忙期のシフト調整が課題となっていました。システム導入により、柔軟な人員配置を実現しています。
導入前の課題
季節変動の大きい売上に対して、適切な人員配置ができていませんでした。また、パートタイム従業員の希望シフトの調整に多大な時間を要していました。店舗間での人員融通も、煩雑な調整が必要でした。
システム導入のポイント
AIによるシフト自動生成機能を導入し、売上予測と従業員の希望を考慮した最適なシフト作成を実現しました。また、店舗間での人員融通を容易にする機能を実装し、柔軟な人員配置を可能にしています。
導入後の成果
シフト作成時間を95%削減し、人件費対売上比率を3ポイント改善しました。また、従業員の希望考慮率が向上し、働きやすい職場環境の実現にも貢献しています。
導入事例から得られる知見
これらの事例から、以下の重要なポイントが導き出されます。まず、業種特性に応じたカスタマイズが成功の鍵となります。また、段階的な導入により、現場の混乱を最小限に抑えることが重要です。
さらに、従業員の利便性と管理側の効率化をバランスよく実現することで、高い効果が得られることが分かります。
以上の導入事例は、勤怠管理システムの効果的な活用方法を示しています。
次章では、システム開発に関するよくある質問について、Q&A形式で解説します。
システム開発タロウくんのQ&A
勤怠管理システムの開発にあたって、よくいただく質問についてシステム開発のエキスパート、タロウくんが分かりやすく解説します。
これらの質問は実際の開発プロジェクトで頻繁に挙がる疑問点を中心に構成しています。
開発期間と導入準備
Q1:開発期間はどのくらい必要ですか?
基本的な機能を備えたシステムであれば、要件定義から本番稼働まで約3〜6ヶ月が目安となります。ただし、既存システムとの連携や、複雑な承認フローが必要な場合は、さらに期間を要する可能性があります。
段階的な導入を行うことで、早期に基本機能の利用を開始することができます。
Q2:既存の人事・給与システムとの連携は可能ですか?
APIを利用した連携が可能です。主要な人事・給与システムについては、標準的な連携方式が確立されており、データ連携の実績も豊富です。
ただし、既存システムの仕様やバージョンによっては、カスタマイズが必要となる場合があります。
機能と運用について
Q3:リモートワーク時の勤怠管理にも対応できますか?
PCのログイン情報やVPNの接続記録と連携することで、リモートワーク時の勤務時間も正確に把握できます。
また、業務開始・終了時のオンライン打刻機能や、業務報告機能を組み込むことで、より詳細な勤務管理が可能です。
Q4:勤務実績のデータ分析は可能ですか?
部署別、従業員別の勤務実績や、残業時間の推移など、多角的な分析が可能です。ダッシュボード機能により、管理者は必要なデータをリアルタイムで確認できます。
また、CSVやExcel形式でのデータ出力にも対応しており、詳細な分析も可能です。
コストと効果
Q5:導入によってどのくらいのコスト削減が期待できますか?
導入事例では、勤怠管理業務の工数が平均で70%削減されています。特に、シフト作成や勤務実績の集計作業において、大幅な効率化が実現できます。
また、適切な人員配置により、人件費の最適化も期待できます。
システムの保守・運用
Q6:システムの保守・運用体制はどのように整備すべきですか?
社内のシステム管理者と開発ベンダーの役割分担を明確にし、定期的なメンテナンス体制を構築することが重要です。
また、ヘルプデスク機能の設置や、マニュアルの整備により、従業員からの問い合わせにも適切に対応できる体制を整えます。
今後の拡張性
Q7:将来的な機能拡張は可能ですか?
モジュール型の設計を採用することで、将来的な機能追加や変更に柔軟に対応できます。また、新しい働き方や法改正にも、システムのアップデートで対応可能です。定期的なバージョンアップにより、最新機能を継続的に提供します。
以上の質問と回答が、システム開発の検討段階でお役に立てば幸いです。さらに詳しい情報や、個別の課題については、お気軽にお問い合わせください。
次章では、本記事の内容をまとめ、今後の展望について解説します。
まとめ
本記事では、勤怠管理システムの開発から運用まで、実践的なアプローチを解説してきました。
ここでは、効果的なシステム開発のための重要ポイントを振り返ります。
開発成功のポイント
勤怠管理システムの開発では、法令順守と業務効率化の両立が重要です。要件定義の段階で現場の声を丁寧に拾い上げ、将来的な拡張性も考慮したシステム設計を行うことで、長期的な運用が可能となります。
今後の展望
働き方改革の進展に伴い、勤怠管理システムにも新たな機能要件が求められています。リモートワークへの対応や、AIを活用した業務効率化など、テクノロジーの進化を取り入れた開発アプローチが今後さらに重要となってくるでしょう。
本記事で解説した実践的な開発手法を基に、御社の状況に合わせた最適なシステム開発を実現していただければ幸いです。
次のステップ
システム開発の検討を始める際は、まず現状の課題を明確化し、段階的な導入計画を立てることをお勧めします。
また、実際の開発着手前に、本記事で紹介した導入事例やトラブルシューティングの内容を参考に、リスク対策を十分に検討することで、スムーズな開発と運用が可能となります。
お問い合わせはこちらから→ ベトナムオフショア開発 Mattock