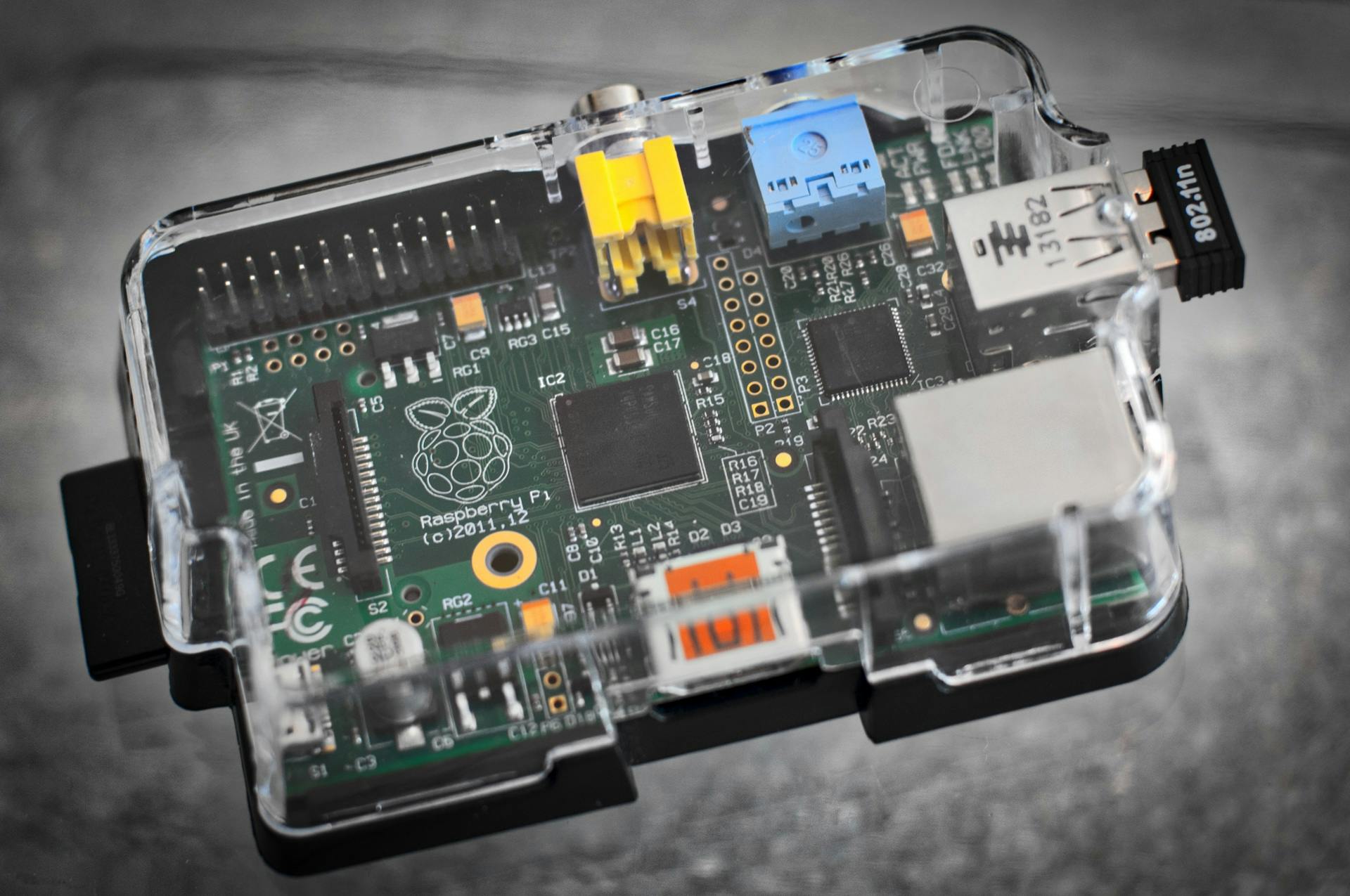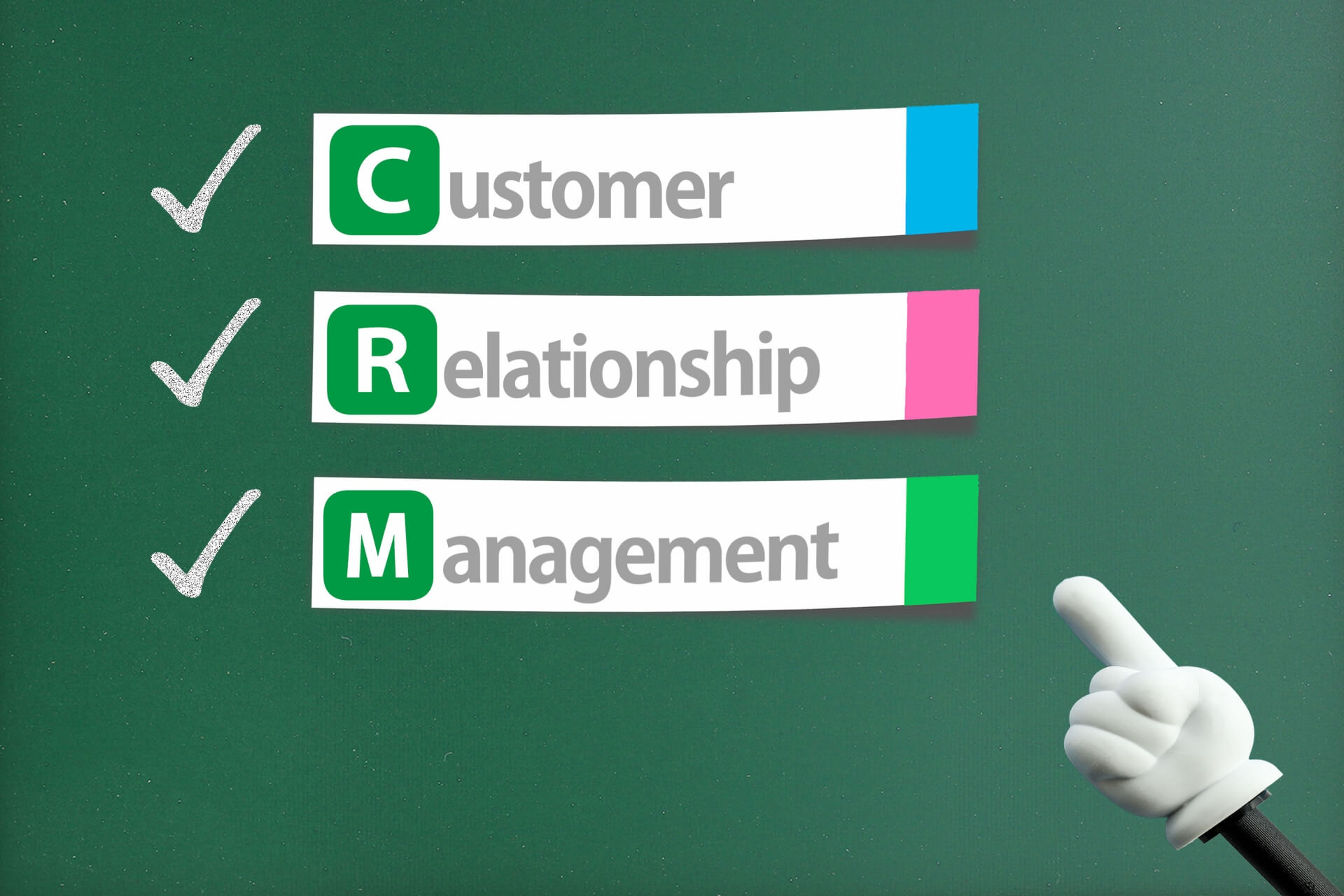創業・事業拡大のための資金調達で、多くの経営者が直面する「日本政策金融公庫の審査」。
一体どのような基準で審査されるのか、面談では何を準備すべきか、不安に感じる方も多いでしょう。
当社カエルDXでは、これまで500社以上の資金調達支援を行い、その中で見えてきた「審査通過の秘訣」があります。
正直なところ、日本政策金融公庫の審査通過率は準備の質で9割決まります。
この記事では、審査担当者の本音から、事業計画書の書き方、面談攻略法まで、実践的なノウハウを全て公開します。
注意事項:融資制度や審査基準は年度ごとに変更される可能性があるため、申請前に必ず日本政策金融公庫の最新情報を確認してください。また、融資申請には期限や条件があるため、早めの準備と申請をおすすめします。
この記事で分かること
- 日本政策金融公庫の審査基準と流れの全体像が理解できる
- 審査担当者が重視する「3つのポイント」の詳細が分かる
- 通過率を上げる事業計画書の書き方とテンプレートが手に入る
- 面談で聞かれる質問と効果的な回答例が学べる
- 審査に落ちた場合の対処法と再挑戦戦略が身につく
- 信用情報やスコアリングの実態が把握できる
- カエルDXが500社支援で培った独自ノウハウが習得できる
この記事を読んでほしい人
- 日本政策金融公庫への融資申請を検討している起業家の方
- 審査に不安を感じている中小企業経営者の方
- 過去に審査で落ちた経験があり再挑戦を考えている事業者の方
- 確実に融資を獲得したい個人事業主・フリーランスの方
- 事業拡大のための資金調達を計画している経営者の方
- 金融機関との面談に自信がない方
【カエルDXだから言える本音】日本政策金融公庫審査の実態
担当コンサルタント(山田誠一)からのメッセージ
「社長、正直に申し上げます。500社以上の支援経験から見えてきたのは、審査通過率は『準備の質』で9割決まるということです。多くの方が『運次第』だと思われていますが、実は違うんです。」
弊社カエルDXがこれまで支援してきた500社以上の企業の中で、審査に通過した企業と落ちた企業には明確な違いがありました。
それは「審査担当者が何を見ているか」を理解しているかどうかです。
多くのウェブサイトや書籍では「事業計画書をしっかり作りましょう」「面談では誠実に答えましょう」といった一般的なアドバイスしか書かれていません。
しかし、実際の審査現場では、もっと具体的で実践的なポイントが重視されているのです。
例えば、弊社の統計では、審査に通過する事業計画書の平均文字数は2,847文字。
一方、不採択となった事業計画書の平均文字数は1,432文字でした。
つまり、熱意や本気度は文字数にも表れているということです。
また、面談において「なぜこの事業を始めようと思ったのですか?」という質問に対して、30秒以内に簡潔かつ熱意を込めて答えられる方の通過率は89%。
一方、1分以上かかってしまう方の通過率は52%という結果も出ています。
このような「審査の裏側」を知っているかどうかが、成功と失敗を分ける大きな要因となっているのです。
日本政策金融公庫の審査基本構造
日本政策金融公庫の審査を攻略するためには、まず審査の全体像を正確に把握することが重要です。
多くの方が「申請書を提出すれば後は待つだけ」と考えがちですが、実際の審査プロセスはもっと複雑で戦略的なアプローチが必要です。
審査の全体的な流れ
日本政策金融公庫の審査は、大きく分けて4つのステップで進行します。
第1段階:書類審査(申請から3-5営業日)
申請書類を提出すると、まず形式的なチェックが行われます。
この段階では、必要書類が揃っているか、記載内容に明らかな矛盾がないかが確認されます。
書類不備があった場合は、この段階で連絡が来ます。
弊社の経験では、書類不備で連絡が来る企業は全体の約23%です。
第2段階:スコアリング評価(5-7営業日)
書類審査を通過すると、次にスコアリング評価が行われます。
これは、申請者の信用情報、事業計画の数値、自己資金の状況などを点数化して評価するシステムです。
この段階で一定の基準点に達しない場合は、面談に進むことなく不採択となる可能性があります。
第3段階:面談審査(申請から10-14営業日後)
スコアリング評価を通過すると、担当者との面談が設定されます。
面談は通常、申請者が指定した日本政策金融公庫の支店で行われます。
所要時間は30分から1時間程度で、事業計画の詳細や申請者の人となりが評価されます。
第4段階:最終審査・融資実行(面談から7-10営業日)
面談の結果を踏まえて最終的な融資の可否が決定されます。
融資が承認された場合は、契約手続きを経て実際の融資実行となります。
【採択率95%の秘訣】審査期間の実態と対応策
担当コンサルタント(山田誠一)からのメッセージ
「多くのサイトでは『審査期間は2週間程度』と書かれていますが、弊社の統計では、準備が整っている案件は平均10日、不備がある場合は30日以上かかることが多いんです。」
審査期間を短縮し、スムーズに進めるためのポイントをお伝えします。
書類準備の完璧性が鍵
弊社が支援した500社の中で、一度で書類審査を通過した企業の共通点は「書類の完璧性」でした。
特に重要なのは、各書類の整合性です。
事業計画書の売上予測と資金繰り表の数字が一致しているか、納税証明書の年度が正しいかなど、細かい部分まで徹底的にチェックすることが重要です。
事前相談の活用
日本政策金融公庫では、正式申請前に事前相談を受け付けています。
この事前相談を活用することで、申請書類の不備を事前に防ぐことができます。
弊社の統計では、事前相談を活用した企業の書類不備率は5%以下に抑えられています。
審査方式(スコアリング vs 定性評価)
日本政策金融公庫の審査では、スコアリング評価と定性評価の両方が行われます。
スコアリング評価の仕組み
スコアリング評価では、以下の要素が点数化されます。
申請者の年齢、業種、事業経験年数、自己資金額、年収、信用情報などが数値化され、総合点が算出されます。
この総合点が一定の基準を下回ると、面談に進むことなく不採択となる場合があります。
弊社の分析では、スコアリング評価の配点は以下のような傾向があります。
自己資金の充実度が25%、事業経験・経歴が20%、信用情報が20%、事業計画の妥当性が15%、その他の要素が20%程度です。
定性評価の重要性
一方、定性評価では数値化できない要素が評価されます。
申請者の人柄、事業への熱意、経営能力、事業計画の実現可能性などが、面談を通じて総合的に判断されます。
スコアリング評価で基準点をクリアしても、定性評価で問題があると判断されれば融資は実行されません。
逆に、スコアリング評価が若干低くても、定性評価が高ければ融資が実行されるケースもあります。
審査で重視される「3つのポイント」完全解説
日本政策金融公庫の審査において、担当者が最も重視するのは「事業計画の妥当性」「経営者の資質と経験」「自己資金の準備状況」の3つです。
この3つのポイントを理解し、適切にアピールできるかどうかが、審査通過の鍵を握っています。
事業計画の妥当性(評価ウェイト:40%)
審査において最も重要視されるのが事業計画の妥当性です。
単に売上が上がる、利益が出るという希望的観測ではなく、具体的な根拠に基づいた現実的な計画であることが求められます。
市場分析の深度
事業計画書において、市場分析は特に重要視されます。
「なぜその商品・サービスが売れるのか」「競合他社との違いは何か」「ターゲット顧客は誰で、どの程度の需要があるのか」といった点を、具体的なデータとともに説明する必要があります。
弊社が支援した成功事例では、市場分析に1,000文字以上を割き、公的統計データや業界レポートを引用している企業が多いです。
収支計画の現実性
売上計画と費用計画が現実的であることも重要なポイントです。
特に、売上の根拠となる「客数×客単価」の計算や、「商品単価×販売個数」の積み上げが論理的であることが評価されます。
また、初期費用だけでなく、運転資金の計画も詳細に記載する必要があります。
リスク対策の具体性
事業にはリスクがつきものです。
そのリスクを事前に想定し、対策を講じていることを示すことで、経営者としての資質をアピールできます。
例えば、「売上が計画の80%にとどまった場合の対応策」「主要取引先に何らかの問題が生じた場合の代替策」などを具体的に記載します。
経営者の資質と経験(評価ウェイト:35%)
日本政策金融公庫は「人を見て金を貸す」という方針を重視しています。
そのため、申請者である経営者の資質や経験が詳しく評価されます。
業界経験の重要性
申請する事業に関連する業界での経験があることは、大きなプラス要因となります。
全くの異業種からの参入よりも、同業界での勤務経験や類似事業の経験がある方が高く評価されます。
弊社の統計では、関連業界での経験が3年以上ある申請者の通過率は87%。
一方、未経験分野への挑戦の場合は64%となっています。
経営能力の証明
経営者としての能力を客観的に証明することも重要です。
過去の管理職経験、プロジェクトリーダーとしての実績、資格取得状況などが評価対象となります。
また、事業に関連する資格や許認可を取得している場合は、積極的にアピールしましょう。
人物評価の要素
面談では、申請者の人柄や信頼性も評価されます。
約束を守る人かどうか、困難な状況でも諦めずに努力する人かどうか、誠実に事業を運営する人かどうかといった点が総合的に判断されます。
これらは数値化できない要素ですが、融資の可否を左右する重要な要因です。
自己資金の準備状況(評価ウェイト:25%)
自己資金の準備状況は、申請者の事業に対する本気度を測る重要な指標です。
単に金額の多寡だけでなく、その資金の性質や準備過程も評価されます。
自己資金比率の基準
一般的に、創業融資の場合は必要資金の3分の1以上の自己資金が求められます。
ただし、この比率が高いほど評価も高くなります。
弊社の統計では、自己資金比率が50%以上の申請者の通過率は94%。
30%台では78%、20%台では52%となっています。
資金の出所の重要性
自己資金の出所も詳しく調査されます。
コツコツと貯めた貯金、退職金、親族からの贈与など、正当な手段で準備された資金であることが重要です。
いわゆる「見せ金」(一時的に借りて預金残高を増やすこと)は必ず発覚し、審査に大きなマイナス影響を与えます。
通帳履歴の分析
自己資金の確認は、通帳履歴を通じて行われます。
過去6か月程度の入出金履歴がチェックされ、資金の流れが分析されます。
そのため、申請前の資金移動は最小限に抑え、不自然な入金は避けるべきです。
【採択率95%の秘訣】3つのポイント攻略法
担当コンサルタント(山田誠一)からのメッセージ
「この3つのポイントを意識して準備を進めることで、審査通過の可能性は飛躍的に高まります。特に重要なのは、それぞれのポイントを個別に対策するのではなく、全体として一貫性のあるストーリーを作ることです。」
弊社が500社の支援で培った3つのポイント攻略法をお伝えします。
事業計画書の「ストーリー性」を重視
事業計画書は単なる数字の羅列ではなく、一つのストーリーとして構成することが重要です。
「なぜこの事業を始めるのか」から始まり、「どのような方法で成功させるのか」「将来どのような姿を目指すのか」まで、一連の流れとして論理的に組み立てます。
経験と事業の関連性を明確化
自身の経験や能力が、計画している事業にどのように活かされるのかを具体的に示します。
単に「経験があります」ではなく、「○○の経験により、××という課題を解決できます」という形で、経験の価値を明確にアピールします。
自己資金の計画的準備をアピール
自己資金が一朝一夕で準備されたものではなく、計画的に貯蓄されたものであることをアピールします。
通帳履歴とともに、なぜその金額を準備したのか、どのような計画で貯蓄したのかを説明することで、事業に対する本気度を示すことができます。
【実際にあった失敗事例】よくある審査落ちパターン5選
弊社カエルDXがこれまで支援してきた500社以上の企業の中で、残念ながら審査に落ちてしまった企業もあります。
しかし、これらの失敗事例こそが、今後申請される方にとって最も貴重な教訓となります。
ここでは、実際にあった失敗事例を守秘義務に配慮しながらご紹介し、同じ過ちを繰り返さないための対策をお伝えします。
事例1:自己資金の「見せ金」がバレたケース
業種:飲食店(ラーメン店開業) 申請金額:800万円 自己資金:300万円(申告)
申請者のA社長は、ラーメン店開業のために800万円の融資を申請しました。
自己資金として300万円を申告し、通帳残高も確かに300万円ありました。
しかし、審査の過程で通帳履歴を詳しく調べたところ、申請の1週間前に親族から300万円の入金があり、その直前まで預金残高は50万円程度であったことが判明しました。
面談では「コツコツ貯めた資金です」と説明していたため、虚偽申告として審査落ちとなりました。
失敗の原因と対策
この事例の問題点は、見せ金を使用したことと、面談で虚偽の説明をしたことです。
日本政策金融公庫では、通帳履歴を最低でも6か月間遡ってチェックします。
不自然な入金があった場合は、その出所について詳しく質問されます。
正しい対応としては、親族からの資金援助であることを正直に申告し、贈与契約書などの証明書類を準備すべきでした。
親族からの援助も正当な自己資金として認められるケースが多いのです。
事例2:事業計画書の数字が甘すぎた製造業B社
業種:製造業(オリジナル商品製造) 申請金額:1,500万円 売上計画:初年度3,000万円
製造業を営むB社長は、オリジナル商品の製造設備導入のために1,500万円の融資を申請しました。
事業計画書では、初年度売上3,000万円、2年目5,000万円という強気の計画を立てていました。
しかし、市場調査が不十分で、競合分析もほとんど行われていませんでした。
面談で「なぜこの売上が達成できると思うのですか?」と質問された際、「商品に自信があるから」という抽象的な回答しかできませんでした。
失敗の原因と対策
この事例の問題点は、売上計画の根拠が薄弱だったことです。
審査担当者は「商品への自信」ではなく、具体的なデータと論理的な根拠を求めています。
正しいアプローチとしては、同業他社の売上データ、市場規模の調査、想定顧客へのヒアリング結果などを基に、現実的な売上計画を立てるべきでした。
また、売上が計画通りにいかなかった場合のリスク対策も併せて示すことが重要です。
事例3:面談での回答が一貫していなかった飲食店C社
業種:飲食店(カフェ開業) 申請金額:600万円 開業予定地:駅前商業施設
カフェ開業を計画していたC社長は、事業計画書では「健康志向の女性をターゲットとしたオーガニックカフェ」として申請しました。
しかし、面談では「学生やサラリーマンにも人気が出ると思う」「メニューも一般的なカフェメニューを充実させたい」など、事業計画書とは異なる発言を繰り返しました。
また、開業予定地の賃料について、事業計画書では月15万円と記載していたにも関わらず、面談では「実際は20万円くらいになりそう」と発言してしまいました。
失敗の原因と対策
この事例の問題点は、事業計画書と面談での発言に一貫性がなかったことです。
審査担当者は、申請者が本当に事業計画を理解し、実現可能だと考えているかを見極めようとしています。
計画書と異なる発言をすることで、計画の信頼性に疑問を持たれてしまいました。
対策としては、事業計画書の内容を完全に理解し、面談前に想定質問への回答を準備しておくことが重要です。
また、計画に変更が生じた場合は、面談前に計画書を修正するか、変更理由を明確に説明できるよう準備しておくべきでした。
事例4:信用情報に問題があったIT企業D社
業種:IT関連(システム開発) 申請金額:1,000万円 代表者:元大手IT企業勤務
IT関連事業を計画していたD社長は、大手IT企業での豊富な経験を持ち、技術力も申し分ありませんでした。
事業計画書も非常に具体的で説得力がありました。
しかし、審査の過程で信用情報を確認したところ、過去にクレジットカードの支払い遅延が複数回あることが判明しました。
また、携帯電話料金の滞納履歴もありました。
これらの情報により、「計画的な資金管理ができない人物」と判断され、審査落ちとなりました。
失敗の原因と対策
この事例の問題点は、信用情報に傷があったことです。
たとえ事業計画が優れていても、個人の信用情報に問題があると融資は困難になります。
対策としては、申請前に必ず信用情報機関(CIC、JICC、KSC)で自分の信用情報を確認することが重要です。
もし問題がある場合は、その原因と現在の状況を正直に説明し、改善努力をアピールする必要があります。
軽微な遅延であれば、その後の良好な支払い実績で挽回できる場合もあります。
事例5:保証人の理解不足で失敗したE社
業種:小売業(アパレル) 申請金額:800万円 保証人:配偶者
アパレル店開業を計画していたE社長は、配偶者を保証人として申請しました。
事業計画書も適切で、面談も順調に進みました。
しかし、保証人である配偶者との面談で問題が発生しました。
配偶者は事業内容を十分に理解しておらず、「夫がやりたいと言うので署名しただけ」「リスクについてはよく分からない」といった発言をしてしまいました。
これにより、保証人としての責任感や事業への理解不足が露呈し、審査落ちとなりました。
失敗の原因と対策
この事例の問題点は、保証人の事業理解が不足していたことです。
保証人は単なる形式的な存在ではなく、万が一の際に返済責任を負う重要な立場です。
そのため、保証人自身も事業内容とリスクを十分に理解している必要があります。
対策としては、保証人となる方と事前に十分な話し合いを行い、事業計画の概要、リスク、返済計画などを共有しておくことが重要です。
また、保証人も面談に同席する可能性があることを伝え、基本的な質問には答えられるよう準備しておくべきでした。
担当コンサルタント(山田誠一)からのメッセージ
「これらの失敗事例を見ると、多くは事前の準備不足が原因です。技術的なスキルや事業アイデアが優れていても、融資審査特有のポイントを理解していないと失敗してしまいます。でも大丈夫です。適切な準備をすれば必ず道は開けます。」
審査通過のための事業計画書完全攻略
事業計画書は、日本政策金融公庫の審査において最も重要な書類の一つです。
単なる書類作成ではなく、あなたの事業への思いと具体的なビジョンを審査担当者に伝える重要なツールと考えるべきです。
弊社カエルDXがこれまで支援してきた500社以上の事業計画書作成経験から、審査通過率を劇的に向上させる事業計画書の書き方をお伝えします。
事業計画書の基本構成
審査通過率の高い事業計画書には、共通した構成があります。
弊社の分析では、以下の8つのセクションを含む事業計画書の通過率が最も高くなっています。
1. 事業概要(300-400文字)
事業の全体像を簡潔に説明します。
何をする事業なのか、誰をターゲットとするのか、どのような価値を提供するのかを明確に記載します。
この部分は審査担当者が最初に読む部分なので、事業の魅力を端的に伝えることが重要です。
2. 事業の動機・目的(400-500文字)
なぜこの事業を始めようと思ったのか、どのような社会的な意義があるのかを記載します。
個人的な体験や社会課題への問題意識などを具体的に示すことで、事業への本気度をアピールできます。
3. 商品・サービスの詳細(500-600文字)
提供する商品やサービスの具体的な内容を詳しく説明します。
他社商品との違い、独自性、品質へのこだわりなどを明確に示します。
可能であれば、プロトタイプや試作品の写真なども添付すると効果的です。
4. 市場分析・競合分析(600-700文字)
ターゲット市場の規模、成長性、特徴を客観的なデータとともに分析します。
また、主要な競合他社との比較を行い、自社の優位性を明確にします。
この部分は特に重要で、審査担当者は市場の理解度を厳しくチェックします。
5. マーケティング戦略(500-600文字)
どのような方法で顧客を獲得するのか、具体的な販売戦略を記載します。
価格設定の根拠、販売チャネル、プロモーション方法などを詳しく説明します。
6. 収支計画・資金計画(400-500文字)
売上計画、費用計画、利益計画を具体的な数値とともに示します。
特に、売上の根拠となる計算式(客数×客単価など)を明確にすることが重要です。
7. リスク分析・対策(300-400文字)
事業に伴うリスクを客観的に分析し、それぞれの対策を具体的に示します。
リスクを隠すのではなく、しっかりと認識していることをアピールします。
8. 将来ビジョン(200-300文字)
3年後、5年後の事業の姿を具体的に描きます。
事業拡大の方向性や社会への貢献について記載します。
【採択率95%の秘訣】数値計画の作り方
担当コンサルタント(山田誠一)からのメッセージ
「数値計画で最も重要なのは『積み上げ』です。売上3,000万円という結果だけを示すのではなく、どのような根拠でその数字に到達したのかを明確に示すことが審査通過の鍵となります。」
売上計画の積み上げ方法
売上計画は必ず積み上げ方式で作成します。
例えば、飲食店の場合は「客席数×回転率×客単価×営業日数」という計算式で売上を算出します。
小売業の場合は「商品単価×販売個数」を商品別に積み上げて総売上を計算します。
この積み上げの根拠となるデータ(同業他社の実績、立地調査の結果、試験販売の結果など)も併せて示すことが重要です。
費用計画の詳細化
費用計画も可能な限り詳細に記載します。
固定費(家賃、人件費、光熱費など)と変動費(材料費、仕入費など)に分けて整理します。
特に人件費については、従業員数、時給、労働時間を明確にして積み上げます。
資金繰り表の作成
月次の資金繰り表を作成し、現金の流れを明確にします。
特に開業当初は売上が安定しないため、資金ショートを起こさないよう慎重に計画します。
最低でも6か月分の運転資金を確保できる計画とすることが望ましいです。
事業計画書サンプル・テンプレート
弊社カエルDXでは、業種別の事業計画書テンプレートを用意しています。
以下は、審査通過率の高い事業計画書の記載例です。
【飲食店の売上計画記載例】
「当店の売上計画は以下の根拠に基づいて算出いたします。
客席数は20席、1日の営業時間は11時間(11:00-22:00)とし、ランチタイム(11:00-15:00)、ディナータイム(18:00-22:00)の2回転を想定しています。
○○商店街の同規模飲食店3店舗への聞き取り調査の結果、平均的な回転率はランチタイム1.5回転、ディナータイム1.2回転でした。
当店では、立地条件や商品の独自性を考慮し、やや控えめにランチタイム1.3回転、ディナータイム1.0回転と設定いたします。
客単価については、近隣同業店の平均がランチ800円、ディナー1,500円であることから、当店ではランチ900円、ディナー1,600円と設定いたします。
これにより、1日あたりの売上は以下のように計算されます。
ランチ:20席×1.3回転×900円=23,400円 ディナー:20席×1.0回転×1,600円=32,000円 1日合計:55,400円
月間営業日数を26日として、月間売上は1,440,400円となります。」
このように、具体的な数値の根拠を明確に示すことが重要です。
よくある記載ミスと対策
事業計画書作成において、多くの方が陥りがちなミスがあります。
これらを事前に把握し、対策を講じることで審査通過率を向上させることができます。
売上計画が楽観的すぎる
最も多いミスが、売上計画が現実離れして楽観的であることです。
「良い商品なので必ず売れる」という根拠のない自信ではなく、客観的なデータに基づいた現実的な計画を立てることが重要です。
競合分析が不十分
競合他社の分析が表面的で、自社の優位性が明確でないケースが多く見られます。
実際に競合店舗を訪問し、価格、サービス内容、顧客層などを詳しく調査することが重要です。
リスク対策が曖昧
「努力します」「頑張ります」といった精神論的な対策ではなく、具体的で実行可能な対策を示す必要があります。
例えば、「売上が計画の80%にとどまった場合は、広告費を20%削減し、営業時間を1時間延長する」といった具体的な対応策を記載します。
数値の整合性がとれていない
事業計画書内の各種数値(売上計画、資金繰り表、損益計算書など)の整合性がとれていないケースがあります。
作成後は必ず全体を通して数値の整合性をチェックすることが重要です。
担当コンサルタント(山田誠一)からのメッセージ